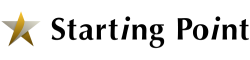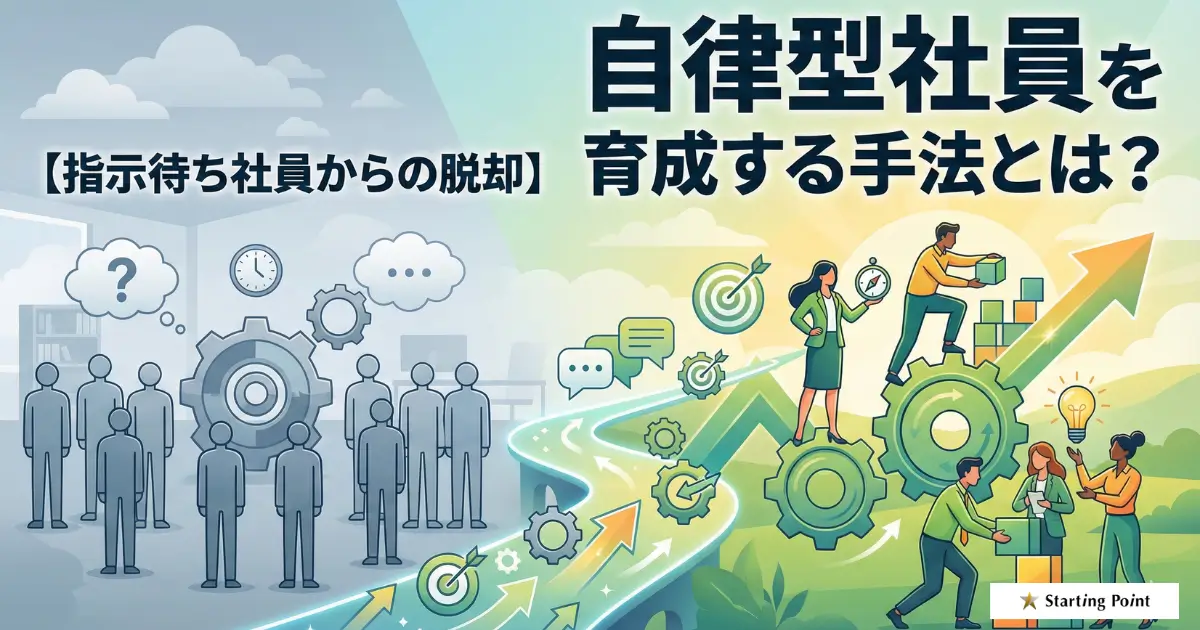
「社員が自分で考えなくなった」「指示待ちの若手が増えている」――こうした悩みは、以前から耳にすることがありました。
しかし最近、ある企業のセルフマネジメント講座を担当した際、私は強い危機感を覚えました。参加者は20代から40代までの幅広い年齢層です。人事担当者は「今回の参加者は意欲がないんですよ」とぼやいていました。
ところが、実際に接してみると、意欲がないのではないことが分かりました。言葉が出てこないのです。聞いた情報を統合する経験がない。考えるための材料が頭の中に不足している――。そうした場面が数多く見られました。
これは個人の資質だけの問題ではありません。組織や社会の構造的な問題でもあると感じています。
「指示待ちで考えなくなった」同じような悩みを抱える経営者や人事担当者は、確実に増えているのではないでしょうか。本記事では、組織から思考力が失われる複合的要因を科学的に分析します。そして、すぐに実践できる具体的な育成方法を解説します。
目次
なぜ今、組織で「考える社員」が減っているのか
組織における思考力低下は、単なる世代の問題ではありません。そもそも考える習慣がない。
考えることが阻まれる複合的な要因を理解することが改善の第一歩です。
不安が脳の思考機能を低下させている【神経科学の知見】
現代の職場では、あらゆる階層で不安が蔓延しています。新入社員は環境適応のストレス、中堅層はキャリアの不透明さ、管理職は経営環境の急激な変化に直面しています。
神経科学の研究によれば、不安状態では脳の扁桃体が過剰に活性化し、論理的思考を司る前頭前皮質の機能が抑制されます(出典:J-Stage 不安症研究)。この状態では、深い思考よりも「反応」が優先され、考える能力が低下するのです。
さらに、慢性的なストレス環境では前頭前野の機能が持続的に低下し、高度な精神機能が損なわれることが明らかになっています(出典:東邦大学 ストレスと脳)。
成長過程で「考える経験」が不足していた【教育システムの影響】
日本の教育に関する国際研究では、批判的思考力の育成が不十分であることが指摘されています(出典:Sage Journals)。
具体的には以下の特徴があります。
- 正解を見つけることが評価の中心
- 自分で問いを立てる訓練が少ない
- 失敗が許容されず、試行錯誤の機会が限られる
こうした環境で育った結果、「問いを持つ」「自分で選択する」「試行錯誤から学ぶ」という思考の基礎スキルが十分に育っていないのです。
「指示に従う」行動が強化されてきた【組織文化の問題】
多くの企業をみてきて、以下のような文化が根づいている組織がいくつもありました。
- 指示に従うことが評価される
- 正解を出せる人が「優秀」とされる
- 意見を言うより「和を乱さない」ことが重視される
行動心理学の原則では、報酬を受ける行動が強化されます。「考えるより正解を探す」「自分で決めるより従う」という行動パターンが評価され続けることで、考えることをやめったケースもあります。
管理職自身が「考えさせる方法」を知らない【育成スキルの欠如】
多くの管理職は、「指示を出す」「答えを教える」という関わり方しか経験していません。部下の思考力を高めるアプローチを知らないため、結果として同じパターンが再生産されています。
「育成スキルの世代間連鎖」が、指示待ち社員を生み出す要因のひとつだと感じています。
考えて動く組織に共通する4つの特徴
一方で、社員が自律的に思考し行動する組織も存在します。その共通点を見ていきましょう。
心理的安全性が確保されている
ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授の研究によれば、心理的安全性の高いチームほど、イノベーション創出能力が優れていることが実証されました(出典:Harvard Business)。
具体的な数字も出ています。2024年の調査では、心理的安全性の高いチームは64%高い生産性を示しました。さらに、従業員エンゲージメントは58%向上しています(出典:Forbes)。
ただし、重要なポイントがあります。それは「安全だが緩くない」環境であることです。
明確な目的があり、適度な緊張感が保たれているからこそ、思考にハリが生まれるのです。安心して意見を言える。しかし、手を抜けるわけではない。この絶妙なバランスが、考える組織を作ります。
「問いの文化」が日常に根づいている
成功している組織では、「どう思う?」「なぜそう考えた?」という問いかけが自然に交わされています。
例えば、星野リゾートでは「正解のない問題と向き合う」「自分の判断や発想で動く」「対立や多様な意見を歓迎する」といった組織文化を醸し出し、思考力を評価する制度やキャリアパスに取り組んでいます(出典:星野リゾートの人気を支える「現地スタッフが考え、決める」仕組み)。
答えを与えるのではなく、考えるきっかけを与える。思考プロセスを引き出す対話が、自律的人材を育てる鍵となります。
小さな実験と振り返りが習慣化している
先進的な組織には、ある共通点があります。「完璧な正解」を求めません。代わりに、「小さくやってみる」ことを奨励する。
重要なのは、失敗を許容するだけでなく、そこから学ぶプロセスを組織が価値として認めること。この文化があるからこそ、社員は安心して試行錯誤できます。そして、その繰り返しが思考力を磨いていくのです。
マネージャーが「育てる関わり方」を実践している
自律的組織のマネジャーは、部下への関わり方が明確に異なります。
具体的には、以下のような4つ関りを実践しています。
| 答えを与えず、問いを投げかける | すぐに正解を教えるのではなく、考えるきっかけを与えます。 |
| 結論より思考プロセスに着目する | 「何を決めたか」ではなく、「どう考えたか」を重視します |
| 部下の意図を言語化させる | 行動の背景にある思いや判断基準を、言葉にする機会を作ります。 |
| 定期的な振り返りの機会を設ける | 経験を学びに変えるため、振り返りを習慣化します。 |
興味深い研究結果があります。奈良教育大学の研究によれば、「指示」ではなく「問いかける言葉」を選ぶことで、学生の専門性が引き出されることが明らかになりました。さらに、多様で活発な議論が生まれ、思考が活性化することも実証されています(参考:奈良教育大学講義で学生の思考を活性化するための「問い」に関する研究講義で学生の思考を活性化するための「問い」に関する研究)。
つまり、マネジメントの「言葉の選択」が、部下の思考力を左右するのです。
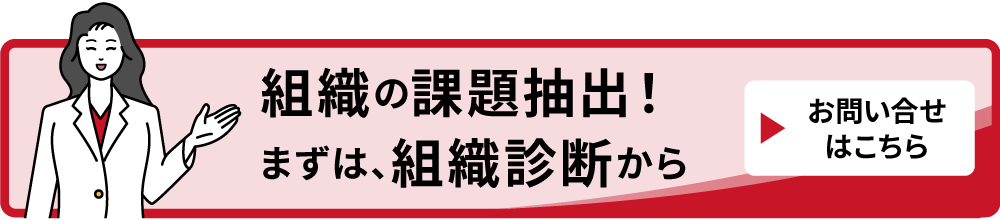
すぐに実践できる!日常で思考力を育む関わり方
明日から始められる、具体的なマネジメント手法を紹介します。
【方法1】指示ではなく「背景・目的」を共有する
単なる指示出しは、思考の機会を奪います。
NG例:「このレポートを明日までに作成してください」
GOOD例:「このレポートは経営陣の戦略検討に使われます。どんな情報があれば意思決定に役立つと思いますか?」
業務の意味が理解できると、社員は自発的に考え始めます。目的を共有し、一緒に考えることで、指示待ちから提案型の行動へと変化していきます。
【方法2】答えの代わりに「質問」を返す
部下から質問を受けたとき、すぐに答えを与えるのではなく、考えさせる問いを返します。
- 「あなたはどう判断しますか?」
- 「他に考えられる選択肢は何がありますか?」
- 「その判断の背景を聞かせてください」
質問がきっかけとなり、思考のスイッチがはいります。考えることに慣れていくと、次第にまずは、自分なりに考えるという思考習慣がうまれていきます。(参考:CMOE Using Questions in Coaching)。
【方法3】思考プロセスを言語化させる
結論だけでなく、「どう考えたか」を言語化させることが重要です。
「その結論に至ったプロセスを、順を追って話してもらえますか?」
慣れていないと自分の考えのプロセスを言葉にすることは難しいことです。ですが、自分の思考パターンを知ることや盲点に気づくことができます。メタ認知能力が育ち、自己改善サイクルが回り始めます。
メタ認知とは、自分自身の思考過程を客観的に把握・評価し、必要に応じて調整・制御する能力のことです。これは1970年代にアメリカの発達心理学者ジョン・H・フラベルによって提唱されました
【方法4】小さな挑戦を促し、失敗を学びに変える
いきなり大きな成果を求めるのではなく、小さな実験を奨励します。
「まず試験的にやってみて、結果を共有してください」
失敗を責めるのではなく、「何を学んだか」に焦点を当てることで、心理的安全性を保ちながら試行錯誤の経験を積ませることが大切です。
【方法5】振り返りを習慣化する
業務の終わりに、以下の3つの問いを習慣化します。
- 「今日は何が起きましたか?」(事実の確認)
- 「それについてどう考えましたか?」(思考の言語化)
- 「次はどういかしますか?」(学びの転移)
メタ認知トレーニングの研究では、継続的な振り返りの効果が明らかになっています。自分の内面に起きた感情や思いを言葉にすることで、問題解決能力や学習効果が顕著に向上することが報告されています。
組織全体で取り組むべき考えて動ける自律的人材の育成アプローチ
日々の関わり方だけでなく、組織として体系的な育成プログラムを設計することが重要です。
自社における「考えて動くとは」の定義を明確化する
企業によって、求める「考えて動く」の具体的な姿は異なります。まず、自社にとっての「考えて動く人材」とは、どのような言動を指すのかを明確に定義しましょう。
定義が曖昧なまま育成を始めても、効果は限定的です。
実は、すべての人は「自分なりに考えて動いている」のです。問題は、そのアウトプットへの期待値にギャップがあることです。
例えば、冒頭で紹介したセルフマネジメント講座でも同様でした。私は一定の発話量や議論の展開を期待していました。ところが、実際には予想以上の静けさでした。そこで、言葉の抽象度を下げて伝えたり、何度も席替えをして変化を与えたりと工夫を重ねました。
その結果、最終日には初日とは見違えるほどの状態になりました。アンケートにも、しっかりと考えた感想が書かれていました。
このように、「考えて動く」の定義を共有し、そのレベルに到達するための具体的な支援を行うことが重要なのです。
思考の発達段階に応じた研修設計
思考力は段階的に発達します。個人の現在地を把握した上で、適切なレベルの課題を与えることが必要です。
<たとえば>
- 新人:具体的な業務での判断練習
- 中堅:複雑な問題の構造化スキル
- 管理職:戦略的思考と育成スキル
発達段階を無視した研修は、効果が出にくいだけでなく、挫折感を生む原因にもなります。
問いを立てるスキルのトレーニング
不確実性の高い時代では、問いの質が成果を左右します。正しい答えを知っているかではなく、本質的な問いを立てられるかが重要です。
しかし、良質な問いを立てるには、高度な思考力が求められます。「何を問うべきか」を考えること自体が、思考のトレーニングになるのです。
研修プログラムには、問いを立てるための思考力を育む要素を段階的に組み込むとよいでしょう。
- 情報を構造化する力を養う
- 前提や思い込みを疑う力を育てる
- 多角的な視点を持つ力を鍛える
- 抽象と具体を行き来する力を磨く
これらの要素を体系的にトレーニングすることで、組織全体の問いの質を高めていけます。
メタ認知能力を高める継続的トレーニング
メタ認知とは、自分の思考について客観的に捉える能力です。
企業研修でメタ認知トレーニングを実施することで、社員が自分の思考の癖を自覚し、改善できるようになります。最新の研究では、メタ認知能力の高いリーダーほどチームパフォーマンスが高いことが実証されています(参考:Research Gate Metacognitive ability and leadership)。
管理職向け「育成スキル研修」を必須化する
マネジメント層の関わり方が変わらなければ、組織文化は変わりません。
思考力を高めるアプローチを修得する内容は、ぜひ管理者研修に含めてほしいコンテンツです。
2024年の調査では、成長マインドセットを持つ従業員がいる企業の80%が利益向上を報告しており、その鍵を握るのが管理職の育成能力です(出典:Forbes)。
5. 環境整備で思考を促進する組織づくり
個人の育成だけでなく、常に考えることが求められる環境を整えることも重要です。
| 評価制度に「思考プロセス」を組み込む | 結果だけでなく、思考プロセスや挑戦姿勢を評価する仕組みを取り入れる。 「どう考えたか」「何を学んだか」が評価されることで、社員は安心して思考を深めることができます。 |
| 情報共有の透明性を高める | 自分で判断するには、判断材料となる情報が必要です。 組織の方針、業績状況、市場動向など、必要な情報を積極的に共有することは、考える材料となります。また、それぞれが受け取れる情報にも配慮が必要です。一方的に伝えるだけではなく、どのように伝わったかを確認することも大切です。 |
| 裁量権を段階的に委譲する | 小さな決定から始めて、徐々に裁量の範囲を広げていく。自分で決める経験の積み重ねが、思考力と自信を育てます。 |
| 失敗を学びに変える文化 | 「失敗は成長の機会」という価値観を組織全体で共有する。 事例を共有する場を設けたり、挑戦を称賛する仕組みを作ることで、心理的安全性が高まります。 |
考える力を育てる
組織から思考力が失われる原因は、個人の資質ではなく、環境と関わり方にあります。
不安が認知機能を低下させ、教育システムが批判的思考を育てず、組織文化が服従を強化してきました。そして管理職自身が育成方法を知らないという構造的問題があります。
しかし、これらは適切なアプローチで改善できます。
今日から始められる5つの実践:
- 指示ではなく背景・目的を共有する
- 答えの代わりに質問を返す
- 思考プロセスを言語化させる
- 小さな挑戦を促す
- 振り返りを習慣化する
組織として取り組むべき施策:
- 自律的人材の定義を明確化する
- 発達段階に応じた研修を設計する
- 問いを立てるスキルを訓練する
- メタ認知能力を高める
- 管理職の育成スキルを強化する
考える力は、偶然育つものではありません。関わりの質と環境の設計によって、意図的に育てることができます。不確実性の高い時代だからこそ、自ら考え、判断し、行動できる人材が組織の競争力を左右します。
「指示待ち組織」から「考える組織」への転換は、まずできるところから始めていきましょう。
【参考文献】
- J-Stage「不安症研究:扁桃体、前頭前皮質」
- 東邦大学「ストレスと脳」
- Sage Journals「Do Japanese students lack critical thinking?」
- Harvard Business「Why Psychological Safety Is the Hidden Engine Behind Innovation」
- Forbes「80% of Companies Say Growth Mindset Drives Profits」
- Research Gate「Metacognitive ability and leader developmental readiness」